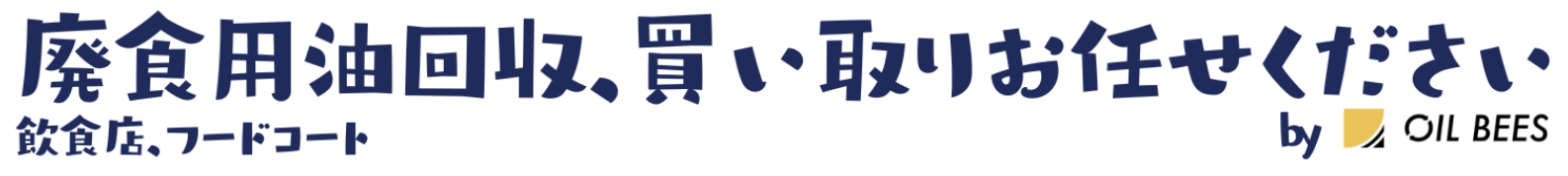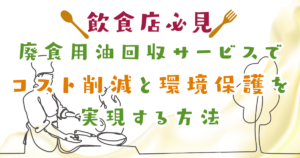はじめに
「油」と聞くと、料理や車のメンテナンス、あるいは原油価格のニュースなど、さまざまなイメージが思い浮かぶのではないでしょうか。
しかし、油は単なる“生活資材”ではなく、私たちの社会、経済、地球環境をつなぐキーワードです。
この記事では、油を切り口に、理科的な視点(性質・物質)と社会的な視点(資源・産業・環境)を交差させ、持続可能な未来のヒントを探ります。
油の正体とは?【理科的視点】
油とは、「水に溶けず、常温で液体である有機物の総称」です。植物油・動物油・鉱物油・合成油などがあり、その用途は食用・潤滑・燃料・化学製品など多岐に渡ります。
- 物性:親油性、疎水性、比重が水より小さい(約0.9前後)
- 熱との関係:発火点・煙点などの安全管理が重要
- 反応性:酸化によって劣化(油臭、変色、粘度変化)する
こうした性質から、油は食品加工や熱エネルギーの伝達、機械部品の保護など、現代の産業基盤に欠かせない存在です。
資源としての油:どこから来て、どう使われているか【社会的視点】
● 食用油の大半は輸入依存
日本では、サラダ油やごま油、オリーブオイルなど、家庭で使われる食用油の多くを大豆・菜種・とうもろこしなどの原材料として海外から輸入しています。原料は主に北米・オセアニア・東南アジア諸国など。
● 石油資源とエネルギー安全保障
日本はエネルギー資源の90%以上を輸入に依存しており、中東地域からの原油供給が地政学リスクに直結しています。石油から得られる潤滑油や軽油・ガソリン・ナフサなどは、自動車・化学産業・物流の血液とも言える存在です。
● 廃食油の行方とリサイクル燃料(バイオディーゼル)
使用済みの食用油(廃食油)は、正しく回収・再利用すれば、バイオディーゼル燃料(BDF)やSAF(持続可能な航空燃料)の原料として有効活用できます。
OIL BEESのような企業が、廃油を資源として再生し、循環型社会の一翼を担っていることも見逃せません。
油がもたらす環境負荷と持続可能性への課題
油にまつわる課題は、資源の枯渇だけにとどまりません。
| 課題項目 | 内容 |
|---|---|
| ごみ問題 | 廃油の不適切処理による水質汚染・配管詰まり |
| 二酸化炭素排出 | 石油燃焼による温室効果ガス排出 |
| 土地利用・生態系破壊 | パーム油栽培のための熱帯雨林伐採 |
| 食料との競合 | 油用作物の増産により食料供給とバッティング |
SDGsとの接点:油を通して見える持続可能な社会の設計図
油に関わるSDGsの主な目標は以下の通りです:
| 目標 | 内容 |
|---|---|
| 7 | エネルギーをみんなに、そしてクリーンに(再生可能エネルギーの推進) |
| 12 | つくる責任・つかう責任(廃油のリサイクル・適正利用) |
| 13 | 気候変動に具体的な対策を(石油燃料の見直し) |
| 14・15 | 海や陸の自然環境を守る(油流出・森林破壊への対応) |
実践的な問い:私たちは「油」とどう向き合うべきか?
家庭や店舗でできること
- 廃油を下水に流さず、回収・リサイクルに回す
- 食用油を過剰に使わず、残さず、丁寧に使い切る
- バイオ燃料やSAFへの理解を深め、支持する企業や製品を選ぶ
企業や教育現場でできること
- 食品ロス削減やエネルギー使用の見直し
- 廃油リサイクル業者との連携(例:OIL BEES)
- SDGsを「ポスター」ではなく「日常業務の中で実践」する教育設計
まとめ:油は「暮らしの質」「産業の構造」「地球の未来」をつなぐ媒介物
油を単なる「調味料」や「エンジンオイル」と捉えるのではなく、
資源・エネルギー・環境・社会の接点として理解することで、
私たちはより多角的に「持続可能な社会とは何か?」を考えられるようになります。
油は目立たないが、現代文明のインフラの一部です。
その価値と責任に目を向けることが、これからの教養と言えるでしょう。