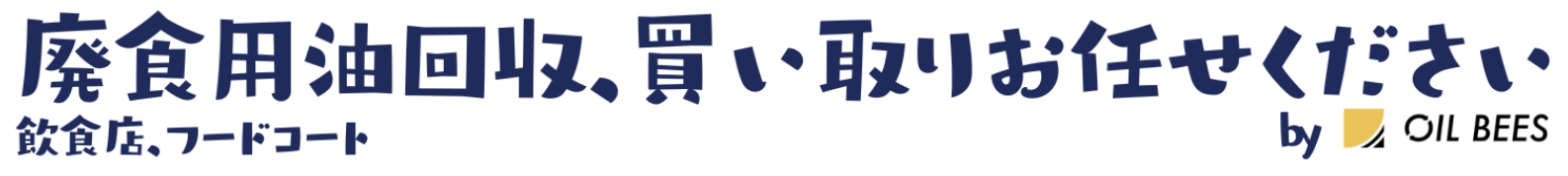なぜ酸化した油をそのまま使ってはいけないのか?
揚げ物や炒め物に欠かせない「油」ですが、使い続けるうちに少しずつ酸化が進みます。酸化した油をそのまま使い続けると、料理の質が下がるだけでなく、健康リスクにもつながることがあります。
料理の味・見た目に与える影響
酸化が進んだ油は、色が濃くなり、揚げ物に焦げたような色や苦味を与えることがあります。せっかく丁寧に調理しても、見た目や味が損なわれてしまえば、お客様の満足度は下がってしまいます。
また、においも独特の「くせ」が出てきて、料理全体に悪影響を与えることがあります。
お客様の健康リスク
酸化した油には、過酸化脂質と呼ばれる物質が増えていきます。これは体内に取り込まれると、胃腸の不調や動脈硬化のリスクを高める可能性があるとされています。
特に小さなお子様や高齢のお客様が多いお店では、安心・安全の観点からも早めの油交換が求められます。
酸化した油を見極める3つのサイン
酸化した油は、見た目やにおい、揚げたときの様子に変化が現れます。プロの厨房でも使える、すぐに実践できる3つのチェックポイントを紹介します。
1 色が濃くなる(透明感がなくなる)
新しい油は透明感があり、ほんのり黄色がかっています。しかし、何度も加熱して使った油は茶色〜黒っぽく濁ってきます。
これは、食材カスや酸素、熱による分解物が混ざり、酸化が進行している証拠です。
油の色が「濃い」と感じたら、そろそろ交換のサインと考えましょう。
2 においがツンとする(刺激臭)
酸化が進むと、油から鼻にツンとくるような独特のにおいが発生します。
例えるなら、古いナッツのようなにおいや、焦げ臭さ、油くささが目立つようになります。
調理前や油を温めたときに、このにおいが強く感じられたら要注意です。新しい油では感じられないにおいです。
3 揚げ物に泡が多く出る
油に食材を入れたとき、必要以上に泡がブクブクと出るようになったら、それも酸化のサインです。
これは、油の表面張力や粘度が変化している証拠で、うまく揚がらず、べちゃっと仕上がってしまうこともあります。
特に泡立ちがひどくなったら、すぐに油の交換を検討しましょう。
酸化を防ぐためにできること
油は一度使い始めると、酸化を完全に止めることはできません。でも、ちょっとした工夫で劣化のスピードを抑えることは可能です。ここでは、飲食店ですぐに取り入れられる対策を3つご紹介します。
こまめな濾過や油量の管理
調理後に残った食材カスをそのままにしておくと、油の劣化が一気に進みます。営業後やアイドルタイムに、油を濾す習慣をつけましょう。
また、鍋に必要以上の油を入れすぎないことも大切です。使いすぎると管理が難しくなり、無駄も増えてしまいます。
火加減・温度管理で劣化を抑える
油の最適な温度は約170~180℃。それを超える高温で加熱しすぎると、急激に酸化が進んでしまいます。
温度計やフライヤーの温度設定機能を活用して、一定の温度を保つように心がけましょう。
調理の合間に火を落とす・保温にするなどの工夫も、油の寿命を延ばすポイントです。
酸化度チェッカーなどの活用
最近では、油の酸化度(劣化度)を数値で測れるチェッカーやテスターもあります。
こういったツールを使えば、「見た目やにおいでは判断が難しい」という方でも、客観的なデータで油の交換時期がわかります。
小規模なお店でも手軽に導入できる機器も増えているので、検討してみるのもおすすめです。