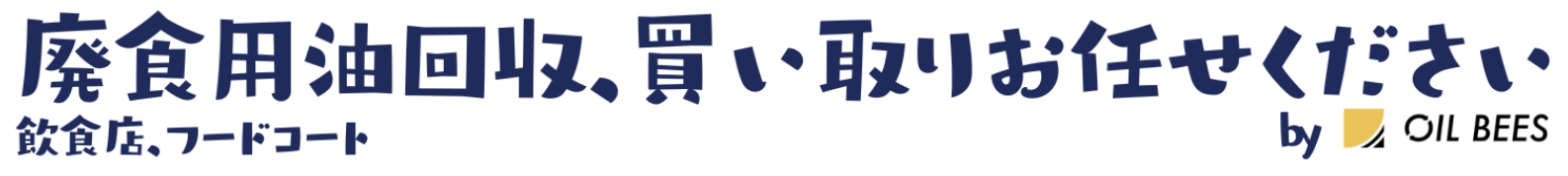1. はじめに:コロナ後に注目される廃油回収市場
2020年以降、飲食店の営業形態が激変。テイクアウトやデリバリー中心の生活様式に移行し、それに伴い廃食用油の発生タイミングや量にも変化が見られます。これを背景に、回収業者は効率化とコスト最適化を迫られています。
2. 廃油リサイクル市場の現状と将来展望
国立環境研究所の調査では、2021年度に出た廃食用油約40万トンのうち、約95%がリサイクルされている(飼料53%、工業原料13%、国内燃料2.6%、輸出燃料32%)。特に輸出先向けの燃料用途が約3割と急増傾向で、環境配慮型の資源循環が加速しています。
3. コスト変動と価格の不安定さ
廃用油の単価は市況によって激しく変動。これにより、飲食店や処理業者は「廃棄物として扱うのか、有価物として扱うのか」の判断に悩む状況が続いています。
また、回収業者間の競争も激しく、低価格での引き取り合戦が発生し、回収–処理コスト削減のプレッシャーが強まっています。
4. 脱炭素・リサイクル推進策と補助制度
環境省や自治体は、廃油分別収集・資源化の導入を加速中。2025年からは地域ごとのCO₂削減目標に連動した分別回収ガイドラインが本格運用されます。
これにより、収集体制やインフラの整備が進み、小規模店舗や地域拠点からの回収効率が改善。輸送・処理コストの削減と一体化した支援が拡大中です。
5. 技術導入による処理効率UPとコスト削減
再生基油やバイオ燃料向けの中間処理技術(脱水・濾過・減圧蒸留など)の導入が進んでいます。
たとえば、潤滑油業界では、再生基油を使うことでCO₂排出量が従来比50〜80%削減され、回収後の精製価値も向上していると報告されています。
これらの技術は食用油処理にも応用可能で、今後コスト削減と高付加価値化に寄与する動きが強まりそうです。
6. SAF開発との連携:環境+収益モデルとして加速
廃食用油をSAF(持続可能航空燃料)原料にする試みも本格化。たとえばレボインターナショナルでは、従来500〜1,000円/kg払っていた廃油を買い取り(5円/kg)、そこで得た油を再処理しSAFへ転換しています。
こうしたBCGモデルは、飲食店にとって廃棄コストの大幅削減+環境アピール効果をもたらしています。今後、SAF関連事業の拡大で回収単価やインセンティブがさらに改善される可能性があります。
7. 事例紹介:都内自治体・企業の取り組み
- 自治体主導の分散型回収拠点:地域センター設置で回収効率アップ、輸送距離短縮によるコスト低減。
- 企業連携プロジェクト:産廃業者と製油所が結びつき、廃油を中間処理→リサイクル燃料や潤滑油に再生。これにより、処理過程のCO₂排出が抑制されています。
8. 今後の注目ポイント
| トレンド | 内容 |
|---|---|
| 自治体ガイドライン整備 | 分別回収の本格的導入で回収効率+コスト削減へ |
| 中間処理技術の普及 | 脱水・精製プロセスの効率化で処理単価◎ |
| SAF・再生燃料事業との連携強化 | 廃油に市場価値がつく構造へシフト |
| 価格安定の仕組み創出 | 長期契約・買い取り保証制度など導入の兆し |
まとめ
- コロナ後の外食形態変化が廃油回収構造にも波及
- 回収・処理コストの不安定要素と業界内競争激化
- 技術・自治体政策・SAF連携により「廃棄→収益」へ転換中
こうした新たな動向を踏まえた上で、以下のような施策が有効です:
- 自治体との連携強化による分散回収拠点整備の支援
- 中間処理技術導入支援による付加価値化およびサービス品質向上
- SAF関連企業とのパートナー構築を通じた回収収益の安定化