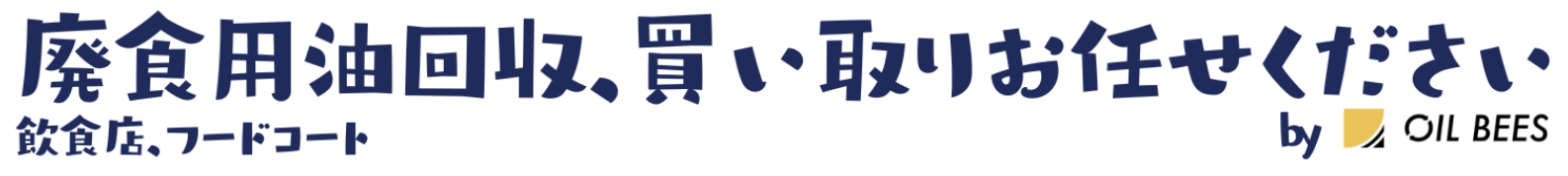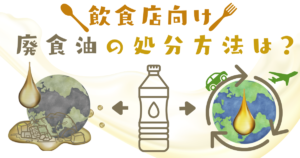なぜ海外で「廃食用油」がビジネスになるのか?
飲食店で日々出る「廃食用油」。日本では「無料で処分してもらえれば助かるもの」という認識が根強いかもしれません。しかし海外では、この廃油が“立派なビジネス資源”として注目されています。なぜ、今、世界は廃油に目を向けているのでしょうか?
最大の理由は、バイオ燃料の原料としての需要の高まりです。とくに欧米では、CO₂排出削減の取り組みが本格化しており、植物由来の再生可能燃料(いわゆる「バイオディーゼル燃料」や「SAF(持続可能な航空燃料)」)への切り替えが急速に進んでいます。これらの燃料の主な原料が、まさに「廃食用油」なのです。
さらに、国をあげての支援も後押しになっています。アメリカではバイオ燃料への補助金制度が整っており、使用済みの油を燃料化して販売する事業者にインセンティブが与えられています。ヨーロッパでも同様に、環境配慮を促す政策の一環として、廃油の再利用が積極的に推進されています。
つまり海外では、「廃油=ごみ」ではなく「資源」として認識されており、それを回収・精製し、エネルギーとして活用する流れが経済として成り立っているのです。
この動きは今や、環境保護だけでなく、新たな雇用や収益を生む産業としても注目されており、“捨てる油”が“儲かる油”に変わりつつあります。
世界の先進事例に学ぶ「廃油の使われ方」
海外では、廃食用油が単なる「不要物」ではなく、積極的にビジネスや社会貢献に活用されています。ここでは、実際に世界で進んでいる廃油活用の事例を紹介します。
アメリカ:ファストフードの“揚げ油”がトラックの燃料に
アメリカでは大手ファストフードチェーンが、店舗で使用した油を回収し、自社の配送トラックの燃料として活用しています。たとえば、マクドナルドの一部店舗では、揚げ物に使った廃油をバイオディーゼルに変換し、物流用の車両に使用。
この取り組みによって、廃棄コストを削減しながら、CO₂排出量も削減するという一石二鳥の成果を上げています。
ヨーロッパ:航空機が“廃油で飛ぶ”時代へ
ヨーロッパでは、航空業界が環境負荷軽減のためにSAF(持続可能な航空燃料)の導入を加速しています。
このSAFの主な原料の一つが、飲食店から出る廃食用油です。例えばオランダの企業SkyNRGは、廃油を精製して航空燃料として供給しており、KLMオランダ航空では実際に商用フライトでの導入が始まっています。
この動きは「空の脱炭素化」の鍵として、今後さらに拡大していくと見られています。
東南アジア:日本の廃油が輸出されている現実
あまり知られていませんが、日本の一部の廃食用油は、すでに海外に輸出されているのが実情です。輸出先は主にアジア諸国で、これらの国では廃油を加工し、燃料や化学製品の原料として再利用しています。
つまり、日本では「ごみ」とされている油が、海外ではお金を払ってでも欲しい資源になっているのです。
なぜ日本では“廃油=ごみ”の意識が根強いのか?

海外では廃食用油が「売れる資源」として扱われているのに対し、日本ではいまだに「捨てるもの」「処分するもの」という意識が根強く残っています。その背景には、いくつかの要因があります。
回収業者の情報が少なく、信頼性に不安がある
多くの飲食店経営者にとって、「廃油を誰にどう渡すか」という情報は決して身近ではありません。
「無料で回収してくれるならどこでもいい」と考え、契約内容や回収後の処理方法まで気にすることは少ないのが現状です。
中には、回収した油の行方が不透明な業者や、法令違反スレスレの処理を行っているケースもあるため、業界全体に対する信頼感が高まりにくいのです。
廃油に“価値がある”という発想がない
日本では「廃油=産業廃棄物」として扱われてきた歴史があり、お金になるどころか、処分費用がかかるものという認識が定着しています。
そのため、「売れる資源になる」という発想がそもそも浮かびにくく、ビジネスチャンスとしても見過ごされがちです。
使用した油がどう再利用されているか、見えにくい
たとえ買取業者に渡していても、「自分の油がどう使われているのか」「どんな形で社会に役立っているのか」が見えないままでは、経営者側も価値を実感できません。
この“見えにくさ”が、「油=捨てるもの」という思い込みを強化してしまっているのです。
しかし、こうした意識は変わりつつあります。
近年では、回収量や買い取り価格をポータルサイトで確認できる業者(例:OIL BEES)も登場し、より透明性のある廃油取引が可能になってきています。
これからの飲食店がすべき3つのアクション
海外のような廃油ビジネスが日本でも広がる可能性は十分にあります。では、飲食店として今できることは何か。ここでは具体的な3つのアクションをご紹介します。
1. 資源としての廃油に意識を向ける
まずは「廃油=ごみ」という意識を見直し、“再利用できる価値ある資源”と捉えることがスタートです。廃油の行き先を知るだけでも、経営への意識が変わってきます。
2. 信頼できる回収業者と契約する(例:OIL BEES)
油を預ける業者は、「無料回収+情報の透明性」がセットであることが望ましいです。OIL BEESでは、ポータルサイトを通じて回収実績や買取金額を可視化し、飲食店側が安心して任せられる仕組みを提供しています。
3. 環境配慮・SDGsの取り組みを小さく始める
廃油の再資源化は、お店の“見えない価値”を高める要素にもなります。たとえば、「おいしい油認定ステッカー」や「環境配慮型店舗」といった発信に活用すれば、地域の信頼や顧客満足にもつながります。
まとめ:海外の流れは必ず日本にも来る
海外ではすでに、廃食用油は「お金を生む資源」として活用されています。この流れは今後、日本にも確実に波及していきます。
飲食店経営者にとって、今はまだ小さな動きに見えるかもしれません。しかし、早めに動いたお店ほど、コスト削減やイメージ向上のメリットを得られるチャンスがあります。
廃油は、もはや“ただのごみ”ではありません。
OIL BEESのような信頼できるパートナーとともに、これからの時代にふさわしい飲食店経営を一緒に進めていきましょう。